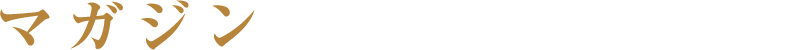萩原朔太郎は明治から昭和にかけての詩人。
「日本近代詩の父」と呼ばれている。
父親は開業医。長男として生まれた朔太郎は、両親から医師として家業を継ぐことを期待されて育てられる。
しかし、幼い時に偶然父親が屍体を解剖している姿を目撃し、ショックを受けた朔太郎は医者にだけはならないと心に決めることになる。
音楽や文学に興味を持ち、落第を繰り返すうち、結果的に父子が衝突するのは宿命だったのかもしれない。
27歳の時、北原白秋が主宰する「朱欒(ザンボア)」に詩を投稿し、その後
現代語を自由自在に駆使し、口語自由詩の美しさを完成させていく。
朔太郎の代表的な詩集「月に吠える」の序文には、以下のような文章がある。
『月に吠える犬は、自分の影に怪しみ恐れて吠えるのである。疾患する犬の心に、月は青白い幽霊のような不吉の謎である。犬は遠吠えをする。
私は私自身の陰鬱な影を、月夜の地上に釘付けにしてしまひたい。影が、永久に私のあとを追ってこないやうに」
朔太郎にとって、詩作は遠吠えであったのだろうか。
父親とは生涯、価値観を共有することなく、朔太郎は後半生には夥しい量の執筆や講演などをこなすようになる。
1942年5月11日、急性肺炎で死去。55年の人生であった。
美しく響くような言葉を持ちながら、「絶望詩人」と呼ばれた世界観に支配されていた朔太郎であった。